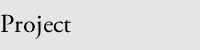
生命倫理に関わるみなさんからの質問に研究者が回答し、議論を共有することを目的としています。
みなさんからのご質問お待ちしています。
【これまでの質問】
子もちの友人が、長年不妊治療をしている(海外在住の)身内から卵子提供の依頼を受け、悩んでいます。頼まれた彼女の判断のよりどころ、ポイントとして、どういうことがあるのでしょうか?アドバイスをお願いします。
倫理学者以外に、神学者や聖職者も聖書の解釈などを通じて動物倫理の議論をしているのでしょうか?何か著名な文献や、各教派の動物に対する公式見解などがあれば教えていただきたいです。
企業に雇用されている弁護士などの法律の専門家は珍しくないですが、最近アメリカの生命科学関係の企業が、倫理学者を雇用しはじめているという話を聞きました。
このような倫理学者の職務とはどのようなものなのでしょう。
またこのような風潮に対し、アメリカ国内外での評価はどうなのでしょうか。
日本はとかくアメリカの動向に影響を受けやすいですが、日本の現状や今後の展望などはどうなのでしょうか。
両論を併記していただいてありがとうございます。
病院倫理委員会に院外委員を招聘する際、報酬をどうするかという問題に通ずるところがあるように思います。
報酬が発生する際の倫理的判断の公正性はどう担保されるのかということですが、できるかぎり活動を公開し批判の対象することで、公正性が維持されるはずと考えるべきなのでしょうね。
生命倫理学者の活躍するフィールドは、今後拡がることはあっても狭まることはないでしょうから、「社会をよくする」という方向さえ見失わなければ、企業に雇用される生命倫理学者も否定されるものではないと理解しました。
ヒトクローンは法律で禁止されていますが、なぜなのでしょうか。
カズオ・イシグロが『わたしを離さないで』で描いたように、臓器提供を目的としたクローン人間作製はその個体の尊厳を傷つけ、許されるものではないと思います。しかし、子どもを産めない人が、生殖医療としてその技術の恩恵に預かることについても、完全に門戸が閉ざされているという印象です。
クローンは、多くの人がイメージしているような核ドナーと全く同じ個体(成体)になる、ということはないと聞きました。であれば、子を授かるための生殖医療としても、検討されていいように思うのですが、そういう検討もなされているのでしょうか。
人のクローンが作られることへの漠然とした恐怖感は私も持っていますが、あまりに漠然としているので、根拠への理解を深めたく、質問をさせていただきます。
ご多忙のところ恐縮ですが、どうぞ、よろしくお願いします。
ご回答、ありがとうございます。安全性の問題以外でヒトクローン作製に反対することは難しいとのことと理解いたしましたが、それは少々驚くものでもありました。
そこで、生物学の研究をしている夫にも意見を求めたところ、目的が生殖医療(子を設けるため)であっても、作成されたクローンは、生物学的には決して“子”ではない、コピーである、というものでした。
そこで、さらにお伺いさせてください。
1. 生物学的に子として認められないヒトを“子”として作成することは、“子”の定義を変えることになるが、そもそも“子”の定義は何なのか。
2. 生物学的に“子”ではなくても、社会的に“子”として法的にも認めるとして、パンドラの箱を開けることにはならないのか。
例えば、ヒトと同様の頭脳を持つロボットをヒトとして認めることを求められたり、愛情を注ぐ対象である犬や猫といったペットにも、財産の所有権を認めることを求められたり、といったことが、とりあえずは思い浮かびます。
3. 自らのコピーを作成したい、などと考える人に悪用されていくと、自然の生命体系を壊していくことにならないのか。
4. 3)を防ぐため例えば、無精子病の患者の不妊治療として認めるとして、遺伝的に同一の子であれば、無精子病という病気もかなりの可能性でコピーされることになり、代々クローンでないと、家系が維持できないような事態を生むが、それでも、その個人の選択として、その医療が提供されていいものなのか。
5. 根拠は説明できないがクローン人間なんてとんでもない、と考える人たちが社会に一定数いるときに、有用な医療行為であり、その技術を必要としている人がおり、安全性が確認されていれば、その医療は導入されていいものなのか。
たくさんお伺いすることになり、申し訳ございませんが、ご教授いただけましたら幸いです。
度重なるご回答、ありがとうございます。
私の説明が不足していたようで、申し訳ありません。
先のご回答から、無性生殖によって人間の子どもを設けることを認めるのか否かが論点になるのかなと理解し、無性生殖で設けた子を人間の子として社会が許容するか、というところをお伺いしたいと考えました。その文脈においての、“人間の子の定義”を意味しておりました。
つまりは、人間の子どもは男性と女性のふたりの遺伝を引き継ぐものでなければならない、といったことを定義してしまうか、あるいは、人間は人間を殺してはならない、というような決まり事と同じように決めてしまえないか、という考えですが、倫理学的に考えると難しいという、当初のご回答があったのでした。。。
ご意見をお伺いし、人間の適正な種の維持を危うくするということが、まずはヒトクローン作成への反論になり得るのだろうと理解いたしました。
同時に、人間は社会を形成し、その社会は個人の尊厳を守ることで維持されているのですから、動物ではよくても、一定のルールで社会を維持する人間では駄目なのだ(厳密なルールが必要だ)、ということかなと思います。(究極のところ、種のバランスが崩れたとして、個体調整を人間ですることはできないですし。)
ご指摘の通り、ヒトクローン作成は医療の範囲を超えていて、生殖医療を目的にヒトクローンを作成する、という問い自体に問題がありました。
これからも、考えていきたいと思います。
ありがとうございました。
できる技術があり、その技術の適応を望む人がいれば、自己決定を根拠に適応していいのかが論点の一つだと思います。
橳島次郎さんの『生命科学の欲望と倫理』によりますと、フランスの生命倫理法では、自己決定よりも上位に、社会秩序の維持、人の種としての尊厳の維持を置いているため、個人の同意がすべてを正当化するわけではないとしているようです。
できる技術を適応してはならないという判断の根拠に関して、このような原則論的な議論が日本ではあまり行なわれていないのではないでしょうか。
(行なわれているのであれば、現状をご教示いただければ幸いです。)
またハーバーマスは、クローンなどからデザイナーベビーへ連なる生殖補助技術は、社会の基盤にあるべき人としての対等性を破壊するという根拠から拒否を正当化できるのではないかと言っていたように思います(『人間の将来とバイオエシックス』)。
もう一点、親の愛情と生の被贈与性は無関係とは思えず、このような技術が親子関係を変えてしまう可能性に対するマイケル・サンデルの懸念も十分に注目すべき点だと思います(『完全な人間を目指さなくてもよい理由』)。
「親となりたい気持ち」は、親の意思のみによる自己決定ですが、そこに生まれてくる子供の意思・自己決定はありません(当然ですが)。これは、本当に無視していいのか、これまでここら辺りの議論が貧弱なため、今更ながら日本では子供の「出自を知る権利」が問題となっているのではないでしょうか。
クローンとして生まれてくる子供の気持ちって、どうなんでしょう?
初めまして。
乱文だと思いますがお付き合い下さい。
私は、大学受験で医療系学部を目指していることもありクローン人間について興味を持ちました。
私は、正直クローン人間について反対です。
確かに、難病を抱えてる方たちからすれば健康体の自分を作ることで患者さん自身にとっては完治する可能性も出てきたりまた拒絶反応なども少なくて済むという点では良いと思った時期もあります。
しかし、小論文などを書くにあたって医療や倫理などいろいろ調べていく中で考えが変わりました。
現在では、クローン人間がもし作られたと仮定した時に何らかの理由で人工的に作られた人間は社会的問題もそうですがクローンとして作られた本人自身の精神的面でも問題があるのではないかと思い私は反対です。
例えば、作った親は本当にそのクローン人間である子供を愛情もって育てる事が出来るかなどです。
クローンとして作られたとしても、人間である以上は感情などをもっているやけです。
目的が終わってしまえば、その人間は必要となくなる可能性があり親は育児放棄をしたり、暴力を振るったりする可能性は多くあると思います。
しかし、クローン人間であっても作ったからにはちゃんと愛情をもって育てるべきだと考えます。
そして、1人の人間として自分自身の人格も持っていると思います。
社会では、クローン人間が問題視されてる大きな理由として臓器移植などの倫理的問題が多く取り上げられていますが、これからもっと考えるべきことは倫理的問題もそうですが、もしクローン人間を作った場合に1人の人格を持った人間としてどのように社会全体が彼らのことを支援していくも考えていくべきだと私は思います。
もし自分自身のクローン人間を作ったとしたら、自分と同じ人格を持った人間だと思いますか?
それとも、違う人格を持った人間だと思いますか?
長文でそして乱文で申し訳ありません。
当初、この質問をさせていただいた者です。先般本HPで公開されたゲノム改変に関する資料を拝読しました。
https://www.cape.bun.kyoto-u.ac.jp/wp-content/uploads/2014/03/e821356ff786e8ddecf8a80936d765a1.pdf
この中で、海外の研究者が次のような指摘をなされていました。
—
「デザイナー」(設計者)と「デザイン(設計) された人々」との間に、非常に非対称的な関係を成立させてしまうというものである。自らのゲノムを改変された人々は、その改変を施した当事者の意図を反映することになるだろう。さらには、親と子の間の関係とは異なり、デザイナーとデザインされた人々との間の関係はその本性上、対話的ではなく、本質的に道具的である。
—
ヒトクローンを作成することも、同様に考えを展開して倫理的に否定することはできないものでしょうか。
つまりは、ヒトクローンで生まれた子どもは「造られた人(被造物)」となり、親は「作成を依頼した人(発注者)」となり、クローニングした人は「造った人(製造者)」となる。そこに人と人との対等な関係性はない。人と人は平等でなくてはならず、人を被造物にすることは平等性の観点から認められるべきではない、という考え方です。
「人は人を造ってはいけない」ということが主張できるのであれば、ヒトクローンは認められないですし、他にも例えば、人間と同じレベルの知能を持つロボットも、「人」として扱われることはあり得ないのではないかと思いました。
前提として、ヒトクローン作成は通常の生殖を補う医療行為ではなく、ヒトを作る行為であるという認識と、人と人が平等でないといけないというのは倫理の玉条のはずであるという(素人)考えがあります。
最初に質問をしたときは、クローン人間はドナーと容姿でさえ同一にはなり得ないと聞いたことでコピー人間を作る不気味さがなくなり、それであれば“子”として存在を認められる可能性もあるのではないか、と考えました。けれど、人が人を造る、という行為そのものをもう一度考え直しました。
やはり無理があるのでしょうか。ご教示いただけましたら幸いです。
色々議論はあったと思いますが、お分りの通り正解は存在しません。定義などという物はその時代の水準によって受け入れられ方は異なる物です。昔はイルカも魚の定義でしたし、また例えばですが
洗濯板が主流の時代に洗濯機が登場すれば、人人は怪訝な見方をするでしょうし、今の私達にとって奴隷制度という物が受け入れられないように。技術という物はそれに相応した時代の水準という物があります。
そういうことなので、現在これだけの反対意見が出るということはクローンという技術に対して時代の水準まだ追いついていないということなのでしょう、
結局の所、良い技術、悪い技術や倫理に反する、倫理に合っているという事は立場によって見方は大きく異なる物です。
良いか悪いかでは答えは出ません、なので出来る限り多くの人が納得できるルール作りが大切な事なんです。それが一番難しいことですけどね
「生まれない方が良いか」
これは、倫理学的には、どのような意味を示しているのでしょうか?
この話題に興味を持ちましたので、横入り失礼いたします。
1.このトピックにおける経験主義に反論する手立ての一つとして、何らかの形で快楽刺激を与え続けて、人生全体の快楽の総量を極端に大きくすれば問題がなくなるだろう、というものがあると思います。経験主義の立場の人はこれに同意するのでしょうか。
2.このトピックの本質は、善悪の線引きに対して快楽/苦痛(快苦)の概念を厳密に適用した場合に何が起こるか、だと思います。他者に苦痛を与える・快楽より苦痛が上回る、これらを「悪」と見なして、悪を排除するためには「生まれてこない方がいい」という結論が出てくるのだと思います。
となると、この議論に対して反論する場合、善悪の線引きに快苦よりも良い手段があるとか、快苦の概念の適用は不適切であるといった方針も取れるように思います。自分で考えた場合、この方針で良い反論が思いつかなかったのですが、議論は存在するでしょうか。
倫理学と技術の進歩について質問させてください。近年、科学研究の分野で、あまりにも先端的すぎるがゆえに(?)、「倫理委員会」のようなものが設けられ、そこに応用倫理を研究する人がメンバーとして加わるということがままあると思います。こうした委員会が設けられる分野としては、従来の人間の生命観や自然観を覆すないし脅かすようなもの、少なくともそれらとは合致しないものの研究があると思います(クローンやiPS細胞)。
こうした科学研究に併設される倫理委員会の役割というものはどういうものなのでしょうか? 委員会内で「この研究はきわめて非倫理的であり、研究を停止することが善である」というような結論が出され、その研究が停止されるというようなこともありえるのでしょうか? それとも単に、「これらの研究は倫理的に問題ありません」と言い、社会の通念に反するかに見える研究にお墨付きを与えるにすぎないのでしょうか? これまで寡聞にして前者のケースについて報告を聞いたことがありません。
大変重要な問いかけをしてくださったと思います。
「科学研究における倫理委員会の役割とは」というご質問ですが、2つの視座から考えたいと思います。
一つは、大学や研究機関に所属する研究者が計画した研究内容を、研究機関内において審査する「研究倫理委員会」の視座です。ご質問の中で、「その研究が停止されるというようなこともありえるのでしょうか」「寡聞にして前者のケースについて報告を聞いたことがありません」とお書きになっているのは、こちらの視座、つまり、個別の研究計画申請への対応を念頭に置かれてのご指摘ではないかと思いました。
各大学や研究機関は、機関内で審査した内容を公表しておりますが、多くは「承認」や「条件付き承認」であり、「承認せず」というケースはほとんどみられないのは事実かと思います。その理由としては、機関内の研究倫理委員会は、既にある各種研究倫理指針で定められた基準に沿って研究が計画されているかを確認するのが第一義的な役割となっているから、ということが言えます。(その意味では、「単に研究にお墨付きを与えている」とも言えるかもしれませんね…。)もうひとつの理由としては、各機関では、委員会に申請する前に、研究計画の内容を専門的立場や事務的な点から助言をする支援体制を整えているところもあり、極端に指針の基準から外れるような計画は、そもそも委員会に上がってこない、ということもあると思います。
なお、私の知る限りの情報で恐縮ですが、ある研究倫理委員会においては、年に1件あるかないかですが、「却下」という判断を下した例が存在することも事実です。しかしその理由は、「従来の生命観や自然観を脅かすような技術であるから」ということではなく、「研究計画が指針のルールに沿っていない、あるいは、きちんとした結果がでるような計画になっていないため」といった、あくまでも、指針上の基準に照らしての判断ということになります。
この「研究倫理委員会」の役割は、例えば、代表的な研究倫理指針である「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」においては、次のように定義されています。「研究の実施又は継続の適否その他研究に関し必要な事項について、倫理的及び科学的な観点から調査審議するために設置された合議制の機関をいう。」
・「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/12/__icsFiles/afieldfile/2014/12/22/1354186_1.pdf
・その他の研究倫理指針については、「ライフサイエンスの広場」も参考になりますhttp://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/index.html
もう一つは、(おそらく質問してくださった方の本質的な問いはこちらだと思うのですが)そういった個々の研究計画の審査ではなくて、全くの新しい技術が登場したときに、それを研究現場(将来的には医療現場)でどう扱うかを総合的に議論する役割としての倫理委員会の視座です。そのような役割は、政府(内閣府)の「生命倫理専門調査会」(http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/life/lmain.html)という組織が担っていると考えています。例えば、ヒトクローン技術やヒトES細胞が登場した時には、まさに、「これらの技術を社会としてどう扱うべきか」ということについて、検討がなされてきました。(その結果、クローン技術については、ヒトの個体を産みだすことにつながる行為は法律で禁止されています。)最新のテーマとしては、「ゲノム編集技術」について、この専門委員会でどのような倫理的課題があるか調査することを決めたということがニュースになっていました。
なお、「生命倫理専門調査会」の役割は、内閣府のサイトによれば「生命科学の急速な発展に対応するため、ヒトES細胞の樹立・使用に関する指針や、特定胚、ヒト胚の取り扱いに関する指針などについての調査・検討を実施」となっています。(内閣府http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/index.html)
まとめますと、以下のようになります。
①一般に「研究倫理委員会」とは、大学や研究機関に設置されていて、研究者が立案する研究計画について、各種研究倫理指針に定める基準に沿って審査をするものである。
②科学研究における全くの新しい技術が登場した場合には、政府(内閣府)の「生命倫理専門調査会」がその技術の取扱いについて検討する場となっている。
しかしです。
ここからは個人的な見解となりますが、①の研究倫理委員会にもまだまだ課題はあります。また、②の専門調査会についても、現在の役割は非常に限定的であり検討する余地があると考えています。特に、生命観や自然観、さらには価値観までも変革するような新しい技術が登場した場合、あるいは、人類の健康や福祉の維持・向上のために大変期待される技術であるけれども、一方で悪用されれば人類を滅亡に至らしめるかもしれないような、諸刃の剣のような技術が登場した場合、私たちはどのように対応することができるでしょうか。
その際重要なのは「私たちはどのような社会に生きたいと考えているのか」という視点を踏まえて検討することだと思っています。また、「技術はある(使える)。求める人もいる。だけど使わない。」という選択をすることも時には必要であると思っています(納得できる理由を考える必要がありますし、なかなか難しい厳しい選択ではあると思いますが)。目先の「役に立つ目的」だけを考えるのではなく、将来(次世代)への視点も持ち合わせる必要があると思っています。
このような議論は、科学研究者や生命倫理の研究者といった専門家だけではなく、一般市民の皆さんと一緒に考えていく必要があります。私たち勝手連では、「新しい技術についてどうする?」ということについて、中身についてもですが、どういうしくみがあれば議論が充実したものにできるのかなども考え、折に触れこのサイトで発信していければと思っていますので、これからの活動にもぜひご注目ください。
横からのコメントで失礼します。
回答者がおっしゃっているように、このような問題を考える上で、「私たちはどのような社会に生きたいと考えているのか」という視点は非常に大事だと思います。これは橳島次郎さんの「我々は現世利益をどこまで追求してよいのか」(『生命科学の欲望と倫理』)という視点と同じで、倫理に“欲望を規制する一定の基準や条件を見つけ出す役割”を求めています。
質問者は、倫理委員会にその役割を担うことを期待されているように思います。しかし、生命倫理だけでそのような欲望を規制する一定の基準や条件を見つけることができるわけもなく、一般市民がどう考えるかが大きなファクターになるんじゃないでしょうか。そこで気になるのが、自由と言いますか、欲望の追求に関して、戦後の知識人たちが、日本人の自由の概念の危うさに触れていた点です。一般市民は、“有用性”と言う言葉に惑わされやすいと思われます。それは資本主義経済が我々の倫理観に与える影響もあるでしょう。しかし回答者も触れておられますが、橳島次郎さんも“有用性”というのは、倫理的判断基準になり得ないと言っています。
将来(次世代)への視点から、我々が現世利益を適切に抑制し、持続可能な社会へとシフトしていくには、社会心理学的なアプローチなども検討する必要があるのではないかと思います。
H.ハーツォグ『ぼくらはそれでも肉を食う』の第二章で、日本人が虫をペットと見なすことを異質なものと見なすかのような記述がありますが(邦訳pp.65-66)、これは平均的なアメリカ人の感覚と理解して良いのでしょうか。また一般に昆虫(ムシ)を動物愛護の対象と見なさないことについて、異論はないのでしょうか(あるとしたらどのようなものでしょうか)。日本人にとっては、「一寸の虫にも五分の魂」という諺通り、虫でも尊重すべきものがあるという感覚があると思います。それが動物愛護に結びつくかどうかは別でしょうけれども。
私は生命倫理学の素人なのですが、今年の9月からアメリカの大学でメディカルスクール志望の学部生向けに15週間の生命医療倫理学の授業をおこなうことになりました。そこで、一般に生命倫理学の授業計画を行う際に参考になるようなサンプルシラバスやアクティビティーなどに関する情報が掲載されているウェブサイトや書籍などをご存知でしたらご教示いただけないでしょうか。
また、私自身素人のため、一から生命医療倫理学を勉強する必要があるので、生命倫理学一般への英語の入門書でできれば人工妊娠中絶や安楽死いった古典的なトピックだけでなくaffordable care actなど近年の動向もカバーしているものをご存知でしたらご教示ください。
ちなみに、教科書にはSteinbock, London, and Arras (eds). (2013). Ethical Issues in Modern Medicine: Contemporary Readings in Bioethics. 8th edition. McGrawHill.が指定されています。
新しい試みでとてもすばらしいと思います。「生命倫理の」ひろばということですが、たとえばプライバシーの理論について質問したら水谷センター長にとりついでいただけたりとかはしないのでしょうか。
ご質問ありがとうございます。生命倫理のひろばは、当面のところ、生命倫理に関係する
ご質問のみをお受けする予定でおります。ただ、「生命倫理のひろば」がうまく運営されれば、
調子に乗って「情報倫理のひろば」「動物倫理のひろば」などが開設されることも
考えられますので、どうぞご期待、またご支援くださいますよう、お願い申し上げます。
なお、現時点では水谷センター長への質問は以下のサイトでお願いします。
http://ask.fm/masayang2010
また、動物倫理に関する質問は以下のサイトがお勧めです。
http://ask.fm/tiseda
それでは今後もどうぞよろしくお願いします。
どんな質問をしたらいいんですか?
「生命倫理のひろば」は、みなさんが「生命倫理」に関してお仕事や日々の生活のなかでお持ちになった疑問を、研究者に対してぶつけていただくという形で共有し、みんなで考えようという場です。
医療や生命科学の倫理に関する素朴な疑問や現行の法制度に関する質問、また、「何か問題があるような気がするけどなにが問題なのかわからない」といったような疑問まで、お気軽にご質問いただければと思います。質問の内容に合わせて適切な担当者がお返事します。
私たち研究者が一方的に答えを示すというよりは、一緒に考える材料を提供できればと考えております。私たちからの返事に対してさらにコメントをつけることもできます。
皆様からのご質問・コメントにより、活発な議論が行われるのを楽しみにしております。
ご質問ありがとうございます。いくつか考えるべきポイントを
挙げてみたいと思います。
まず、その国の制度を確認する必要があるかと存じます。匿名第三者からの卵子提供は、日本でも少し前に問題になりましたが(下記1参照)、身内(家族)や知り合いからのボランティアの卵子提供に関わる法制度について確認されるのがよいかと存じます。原則として卵子提供や出産を行う国の法律が適用されるので、よくご確認ください。
次に、卵子提供に伴う健康リスクについて医師等によく相談するのがよいかと存じます。少し前にeggsploitationというドキュメンタリー(下記2参照)で卵子提供の問題が批判的に論じられておりましたが、排卵誘発剤の使用などに伴なう母体への健康リスクについてよく知っておく必要があるかと存じます。
第三に、匿名第三者ではなく親族が卵子を提供することに伴う問題があるかと思います。卵子を提供して子どもが生まれると遺伝上は自分の子どもということになるため、仮に法的には自分の子どもでなかったとしても、ドナーの女性と、産んだカップルとの関係が大きく変容することが考えられます。今後も良好な関係を保つことができるか、よく考える必要があります。
第四に、上記の点と関連して、子どもに卵子提供の事実を伝えるかどうかも問題になるかと思います(これは子どもの出自を知る権利についての法制度も確認する必要があります)。第三の点や第四の点は、身内とはいえ、事前にしっかり取り決めをしておかなければ、あとで関係がこじれる恐れがあるかと存じます。
最後に、以上のように述べてきましたが、私は不妊治療としての卵子提供に反対しているわけではないので、上記のリスクや問題をよく考慮したうえでなら、身内を助けると思って卵子提供をやってみてもよいのではないかと思います。もちろん不妊治療をしているカップルは、不妊治療で相当の苦労し、また養子等の選択肢も考えられたうえで、あえて身内の方に頼もうとしているのだと想像します。子どもをもちたいという切なる望みを助けることができるならば、大きな障害がないかぎり、そうしたらよいのではないかと存じます。
以上ですが、卵子提供の際にはカウンセリングを受けるなど、上記の点やその他の心配事について十分に相談することをお勧めします。
1 匿名の卵子で体外受精 国内初、神戸の団体仲介
神戸新聞NEXT 2015/7/27
http://www.kobe-np.co.jp/news/iryou/201507/0008248965.shtml
2 eggsploitation
http://www.eggsploitation.com/