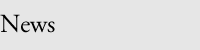
ヒトクローンは法律で禁止されていますが、なぜなのでしょうか。
カズオ・イシグロが『わたしを離さないで』で描いたように、臓器提供を目的としたクローン人間作製はその個体の尊厳を傷つけ、許されるものではないと思います。しかし、子どもを産めない人が、生殖医療としてその技術の恩恵に預かることについても、完全に門戸が閉ざされているという印象です。
クローンは、多くの人がイメージしているような核ドナーと全く同じ個体(成体)になる、ということはないと聞きました。であれば、子を授かるための生殖医療としても、検討されていいように思うのですが、そういう検討もなされているのでしょうか。
人のクローンが作られることへの漠然とした恐怖感は私も持っていますが、あまりに漠然としているので、根拠への理解を深めたく、質問をさせていただきます。
ご多忙のところ恐縮ですが、どうぞ、よろしくお願いします。
ご回答、ありがとうございます。安全性の問題以外でヒトクローン作製に反対することは難しいとのことと理解いたしましたが、それは少々驚くものでもありました。
そこで、生物学の研究をしている夫にも意見を求めたところ、目的が生殖医療(子を設けるため)であっても、作成されたクローンは、生物学的には決して“子”ではない、コピーである、というものでした。
そこで、さらにお伺いさせてください。
1. 生物学的に子として認められないヒトを“子”として作成することは、“子”の定義を変えることになるが、そもそも“子”の定義は何なのか。
2. 生物学的に“子”ではなくても、社会的に“子”として法的にも認めるとして、パンドラの箱を開けることにはならないのか。
例えば、ヒトと同様の頭脳を持つロボットをヒトとして認めることを求められたり、愛情を注ぐ対象である犬や猫といったペットにも、財産の所有権を認めることを求められたり、といったことが、とりあえずは思い浮かびます。
3. 自らのコピーを作成したい、などと考える人に悪用されていくと、自然の生命体系を壊していくことにならないのか。
4. 3)を防ぐため例えば、無精子病の患者の不妊治療として認めるとして、遺伝的に同一の子であれば、無精子病という病気もかなりの可能性でコピーされることになり、代々クローンでないと、家系が維持できないような事態を生むが、それでも、その個人の選択として、その医療が提供されていいものなのか。
5. 根拠は説明できないがクローン人間なんてとんでもない、と考える人たちが社会に一定数いるときに、有用な医療行為であり、その技術を必要としている人がおり、安全性が確認されていれば、その医療は導入されていいものなのか。
たくさんお伺いすることになり、申し訳ございませんが、ご教授いただけましたら幸いです。
度重なるご回答、ありがとうございます。
私の説明が不足していたようで、申し訳ありません。
先のご回答から、無性生殖によって人間の子どもを設けることを認めるのか否かが論点になるのかなと理解し、無性生殖で設けた子を人間の子として社会が許容するか、というところをお伺いしたいと考えました。その文脈においての、“人間の子の定義”を意味しておりました。
つまりは、人間の子どもは男性と女性のふたりの遺伝を引き継ぐものでなければならない、といったことを定義してしまうか、あるいは、人間は人間を殺してはならない、というような決まり事と同じように決めてしまえないか、という考えですが、倫理学的に考えると難しいという、当初のご回答があったのでした。。。
ご意見をお伺いし、人間の適正な種の維持を危うくするということが、まずはヒトクローン作成への反論になり得るのだろうと理解いたしました。
同時に、人間は社会を形成し、その社会は個人の尊厳を守ることで維持されているのですから、動物ではよくても、一定のルールで社会を維持する人間では駄目なのだ(厳密なルールが必要だ)、ということかなと思います。(究極のところ、種のバランスが崩れたとして、個体調整を人間ですることはできないですし。)
ご指摘の通り、ヒトクローン作成は医療の範囲を超えていて、生殖医療を目的にヒトクローンを作成する、という問い自体に問題がありました。
これからも、考えていきたいと思います。
ありがとうございました。
できる技術があり、その技術の適応を望む人がいれば、自己決定を根拠に適応していいのかが論点の一つだと思います。
橳島次郎さんの『生命科学の欲望と倫理』によりますと、フランスの生命倫理法では、自己決定よりも上位に、社会秩序の維持、人の種としての尊厳の維持を置いているため、個人の同意がすべてを正当化するわけではないとしているようです。
できる技術を適応してはならないという判断の根拠に関して、このような原則論的な議論が日本ではあまり行なわれていないのではないでしょうか。
(行なわれているのであれば、現状をご教示いただければ幸いです。)
またハーバーマスは、クローンなどからデザイナーベビーへ連なる生殖補助技術は、社会の基盤にあるべき人としての対等性を破壊するという根拠から拒否を正当化できるのではないかと言っていたように思います(『人間の将来とバイオエシックス』)。
もう一点、親の愛情と生の被贈与性は無関係とは思えず、このような技術が親子関係を変えてしまう可能性に対するマイケル・サンデルの懸念も十分に注目すべき点だと思います(『完全な人間を目指さなくてもよい理由』)。
「親となりたい気持ち」は、親の意思のみによる自己決定ですが、そこに生まれてくる子供の意思・自己決定はありません(当然ですが)。これは、本当に無視していいのか、これまでここら辺りの議論が貧弱なため、今更ながら日本では子供の「出自を知る権利」が問題となっているのではないでしょうか。
クローンとして生まれてくる子供の気持ちって、どうなんでしょう?
初めまして。
乱文だと思いますがお付き合い下さい。
私は、大学受験で医療系学部を目指していることもありクローン人間について興味を持ちました。
私は、正直クローン人間について反対です。
確かに、難病を抱えてる方たちからすれば健康体の自分を作ることで患者さん自身にとっては完治する可能性も出てきたりまた拒絶反応なども少なくて済むという点では良いと思った時期もあります。
しかし、小論文などを書くにあたって医療や倫理などいろいろ調べていく中で考えが変わりました。
現在では、クローン人間がもし作られたと仮定した時に何らかの理由で人工的に作られた人間は社会的問題もそうですがクローンとして作られた本人自身の精神的面でも問題があるのではないかと思い私は反対です。
例えば、作った親は本当にそのクローン人間である子供を愛情もって育てる事が出来るかなどです。
クローンとして作られたとしても、人間である以上は感情などをもっているやけです。
目的が終わってしまえば、その人間は必要となくなる可能性があり親は育児放棄をしたり、暴力を振るったりする可能性は多くあると思います。
しかし、クローン人間であっても作ったからにはちゃんと愛情をもって育てるべきだと考えます。
そして、1人の人間として自分自身の人格も持っていると思います。
社会では、クローン人間が問題視されてる大きな理由として臓器移植などの倫理的問題が多く取り上げられていますが、これからもっと考えるべきことは倫理的問題もそうですが、もしクローン人間を作った場合に1人の人格を持った人間としてどのように社会全体が彼らのことを支援していくも考えていくべきだと私は思います。
もし自分自身のクローン人間を作ったとしたら、自分と同じ人格を持った人間だと思いますか?
それとも、違う人格を持った人間だと思いますか?
長文でそして乱文で申し訳ありません。
当初、この質問をさせていただいた者です。先般本HPで公開されたゲノム改変に関する資料を拝読しました。
https://www.cape.bun.kyoto-u.ac.jp/wp-content/uploads/2014/03/e821356ff786e8ddecf8a80936d765a1.pdf
この中で、海外の研究者が次のような指摘をなされていました。
—
「デザイナー」(設計者)と「デザイン(設計) された人々」との間に、非常に非対称的な関係を成立させてしまうというものである。自らのゲノムを改変された人々は、その改変を施した当事者の意図を反映することになるだろう。さらには、親と子の間の関係とは異なり、デザイナーとデザインされた人々との間の関係はその本性上、対話的ではなく、本質的に道具的である。
—
ヒトクローンを作成することも、同様に考えを展開して倫理的に否定することはできないものでしょうか。
つまりは、ヒトクローンで生まれた子どもは「造られた人(被造物)」となり、親は「作成を依頼した人(発注者)」となり、クローニングした人は「造った人(製造者)」となる。そこに人と人との対等な関係性はない。人と人は平等でなくてはならず、人を被造物にすることは平等性の観点から認められるべきではない、という考え方です。
「人は人を造ってはいけない」ということが主張できるのであれば、ヒトクローンは認められないですし、他にも例えば、人間と同じレベルの知能を持つロボットも、「人」として扱われることはあり得ないのではないかと思いました。
前提として、ヒトクローン作成は通常の生殖を補う医療行為ではなく、ヒトを作る行為であるという認識と、人と人が平等でないといけないというのは倫理の玉条のはずであるという(素人)考えがあります。
最初に質問をしたときは、クローン人間はドナーと容姿でさえ同一にはなり得ないと聞いたことでコピー人間を作る不気味さがなくなり、それであれば“子”として存在を認められる可能性もあるのではないか、と考えました。けれど、人が人を造る、という行為そのものをもう一度考え直しました。
やはり無理があるのでしょうか。ご教示いただけましたら幸いです。
色々議論はあったと思いますが、お分りの通り正解は存在しません。定義などという物はその時代の水準によって受け入れられ方は異なる物です。昔はイルカも魚の定義でしたし、また例えばですが
洗濯板が主流の時代に洗濯機が登場すれば、人人は怪訝な見方をするでしょうし、今の私達にとって奴隷制度という物が受け入れられないように。技術という物はそれに相応した時代の水準という物があります。
そういうことなので、現在これだけの反対意見が出るということはクローンという技術に対して時代の水準まだ追いついていないということなのでしょう、
結局の所、良い技術、悪い技術や倫理に反する、倫理に合っているという事は立場によって見方は大きく異なる物です。
良いか悪いかでは答えは出ません、なので出来る限り多くの人が納得できるルール作りが大切な事なんです。それが一番難しいことですけどね
ご質問ありがとうございます。1997年のクローン羊ドリー誕生の報道以来、哺乳類では牛や馬、猫や犬などで体細胞クローンが成功しています。人に関しても、人クローン胚の作製が2005年に成功しております。上記の哺乳類動物でも実際に健康に成長する個体はほとんどいないということなので、現在クローン人間を作ることに対する最も重要な反論は母体および子どもに対するリスクの大きさだと言えます。
しかし、研究が進めば、クローン人間を安全に作ることができるようになるかもしれません。その場合に、原則として禁止する根拠があるかどうかは明らかではないように思います。「人の尊厳を侵す」という批判や、「無性生殖は自然に反する」という批判などがありますが、犬や猫の場合は、自然に反することも犬や猫の尊厳を侵すことがないのに、人間だけダメという理由を正確に述べるのは難しいと思います。また、仮に遺伝的に同一の個体が生まれるとしても、時間差のある双子だと考えれば、それほど問題であるようには思えません。
「わざわざクローン人間という手段を用いなくても子どもを持つ方法はある」という批判も考えられます。たしかに、iPS細胞等から生殖細胞を作製できる可能性も現実味を帯びてきたこともあり、クローン技術を使う以外には子どもを持つ方法がないというのは考えにくいかもしれませんが、これは積極的に禁止する理由にはならないように思われます。
というわけで、私は個人的には人のクローン個体の作製について、まだ安全ではないという理由を除けば、倫理的な問題は感じておりません。クローン個体を積極的に作る理由もあまりないように思いますが、近い将来、iPS細胞等を用いた生殖医療について考えていくさいには、クローンの問題も再度検討すべきなのかもしれません。
参考:
THE SCIENCE OF HUMAN CLONING: HOW FAR WE’VE COME AND HOW FAR WE’RE CAPABLE OF GOING
http://www.bioethics.com/archives/28173
Human stem cells made using Dolly cloning technique
http://www.newscientist.com/article/mg21829174.200-human-stem-cells-made-using-dolly-cloning-technique.html#.VZp7a3ggxuE
児玉聡・なつたか『マンガで学ぶ生命倫理』化学同人、2013年、第7章「クローン技術」