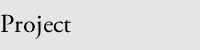
| « 9月 | 11月 » | |||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ゲノム編集技術の科学的、医療的可能性と倫理的な問題についての最新の提言を、日本語でコンパクトにご確認いただけます。 去る2015年9月29日、「ゲノム編集の見込みと限界」というタイトルで、DFG(ドイツ研究振興協会)はドイツ国立学術アカデミーレオポルディーナ、ドイツ科学技術アカデミー、ドイツ科学アカデミー、計三つのアカデミーと共同して声明を発表しました。 田中創一朗さ、服部高宏さん、当センター員の児玉聡先生による、声明の要約(日本語)を資料として「プロジェクト生命倫理」のページに公開いたしました。こちらからご覧ください。
去る10月17日(土)本学文学研究科にて第1回「研究公正の理念の学際的検討と日本的な研究倫理の構築」研究会を開催しました。 当センター員の伊勢田哲治先生のご講演は、「研究不正は本当に悪いのか、悪いとしたら、どのような理由で悪いのか」という問題を論じるものでした。研究不正が論じられるとき、ねつ造と盗用・改ざんといった不正内容の分類の区別が考慮されない、不正とされる論拠が雑多であるなど、整理すべき論点を取り上げていただきました。 国内における研究公正研究を代表する研究者でもある愛知淑徳大学の山崎茂明先生には、主として実験・調査の必要な生命系や理工系の分野における研究不正の問題を豊富なサーベイを基に…
3マールカJSB様からお寄せいただいたコメントに対する児玉聡先生の回答を掲載しました。 安全性を除いては倫理的にクローン人間を否定する理由はないという児玉先生の立場に対し、ヒトクローンを許容すると関連して社会的問題が様々に生じうるのではないかというご指摘です。 児玉先生の回答はこちらからご覧ください。
去る10月3日(土)に開催された、市民と研究者の対話を目的とする京都大学アカデミックデイ2015に出展し、「ゲノム編集の倫理を考える」(参加者:児玉聡(出展代表者)、田中 創一朗、佐藤恵子、鈴木美香)というポスターセッションを行いました。 この度、発表に使用したポスター、および当日行ったアンケート調査の結果をプロジェクトページ「生命倫理」に公開しました。 トウモロコシやリンゴなどの遺伝子組み換え作物をはじめ遺伝子改変技術がすでに生活に浸透している中で、会場に足を運んでくださった皆さまと活発な意見交換を行うことができました。当日の報告とあわせてぜひご一読下さい。
生命倫理に係るプロジェクトの一環として、この度、幹細胞と倫理・法に関する国際的コンソーシアムであるヒンクストン・グループ゚によるゲノム編集声明概要を公開いたしました。 詳細はプロジェクト生命倫理のページでご覧ください。
satoko様からいただいた「死体からの強制的臓器抽出についての質問」への児玉聡先生の回答を掲載しました。 権利ももたず快苦も感じない死体から臓器を強制的に摘出し、移植の必要な人に提供することを批判する哲学的、倫理的根拠はあるのでしょうか。 児玉先生の回答はこちらからご覧ください。