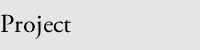
| « 7月 | ||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
去る11月27日(金)に本学文学部校舎でロボット倫理についてのCAPEワークショップを開催しました。
前半は、滋賀大学の神崎宣次先生がオーガナイザーを務める日本のロボットをめぐる社会状況についてのディスカッション。
2015年4月に起きた首相官邸ドローン落下事件や、9月に成立したドローンの利用場所や大きさを制限する改正航空法(ドローン規制法)、それらに対する法律の専門家の意見などを紹介。
ドローン規制法が性急だと批判される中で、リスクを予想してあらかじめそれを回避するため事前規制を念頭におくべきか、自由な研究、経済活動を保障した上で事件が起きた後の補償をを重視するか、というリスクについての向き合い方が問題となりました。
後半は、モナシュ大学のロバート・スパロー先生の講演で、殺傷能力のある軍事ロボットの利用を禁じるべき根拠について論じていただきました。
その根拠として、直接人を殺傷するわけではないがゆえに、操作する人間の戦闘行為への心理的抵抗感が減ってしまい、安易な殺戮に結び付く危険性がある、というもの、
敵・味方、民間人と戦闘員の識別機能がロボットの場合、人間に比べて低いということがあげれられました。
また、「戦闘行為にも倫理規範が存在する。意思をもたない機械によって殺されることは人の尊厳を損なう望ましくない行為である」という論点が提示され、これについて特に議論が盛り上がりました。