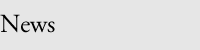
最近培養肉というものが開発されていますがそれについて動物倫理学の理論的にどうなんですか?
シンガー流の考え方ならまず認められそうですがレーガン的な考え方の場合はどうなんでしょうか?
あと前の質問は理論的なものですが培養肉に対して動物倫理学界では培養肉に対してどのような評価なのでしょうか?
動物愛護団体などの見方などはよく見るのですが動物倫理学者もそれと同じなのかどうなのかは気になるところです。
培養肉自体まだ実用化しておらず発展途上の分野であるのでどれくらい倫理学者から注目されてるかわかりませんが回答お願いします。
ご質問ありがとうございます。応用哲学倫理学教育研究センターのプロジェクトの一つ、人と動物の倫理研究会でも、2017年3月に開催した第四回研究会で培養肉の話題を取り上げたところです。
https://www.cape.bun.kyoto-u.ac.jp/capes/ws/#ws170320
そのときうかがった話では、培養肉は今のところ培養液に動物由来の素材を使うのでアニマルライツ的な視点から問題がないとはいえないということでしたが、そこは技術改良で乗り越えられる問題なのだろうとおもいます。その点が乗り越えられたとしたら、という前提の下でお答えします。
まず、シンガーなどの功利主義的な観点から考えると、もちろん培養肉は苦しまないでしょうから、その点で苦痛は明らかに削減されています。しかし、功利主義的判断はトータルな影響を考慮する必要がありますし、具体的にどの選択肢と比較するかというのも大事です。仮に培養肉がエネルギーを大量に消費し、その悪影響が非常に大きい場合、工場畜産の方がましだったと判断することはないとはいえないでしょう。また、仮に世界の情勢が、なにもしなくても肉食から大豆食への移行がすすみつつある、というようなものだった場合、培養肉を促進したために大豆食への移行がかえって遅れる、というようなシチュエーションも考えられて、総合評価として培養肉の推進はやめておいた方がいい、ということはありえます。こういうこともあるので、功利主義による判断はケースバイケースにならざるをえないと思います。
レーガンの方がこうした点についてはシンプルです。培養肉はそれ自体としては明らかに彼の定義するところの「生の主体」ではなく、したがって尊重される必要はありません。培養肉を食べることを積極的に勧めはしないけれど禁止もしない、というような立場になるでしょう。
培養肉への反感の一部は、それが生命に対する操作をもう一段階進めるように思えること、それが生命というものの軽視やなんでも操作できるという人間の傲慢さの現れのように見えること、などからきていると思われます。これはある種の徳倫理学的な発想だと思われます。しかし、倫理学の議論の中で、こういう考え方をシンガーやレーガンに対するまともな対抗馬として定式化するのは非常に難しいというのが現状です。